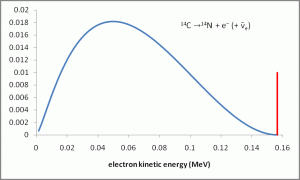第一近似として,ニュートリノは質量を持たず,何ものとも相互作用しないので検出は不可能です。それでは,なぜニュートリノの存在が予言されたのでしょうか? それは,原子核の放射性崩壊の一種であるβ崩壊の研究から始まりました。β崩壊では,原子番号Zの原子核が原子番号Z+1の原子核に転換するとともに1個の電子を放出します。β崩壊の例として,考古学の年代測定に使われる,炭素14から窒素14への崩壊:14C → 14N + e– があります。
β崩壊は,娘核の質量が親核の質量よりも小さく,崩壊した方がエネルギー的に有利になる場合に起こります。アインシュタインの方程式 E = mc2 によって,初期の原子核物理学者は,親核と娘核の質量差を電子が運動エネルギーの形で持ち去ると期待していました。しかし,電子はいつも期待されたエネルギーよりも少ないエネルギーしか持っていないことが分かりました。しかも,2体崩壊から予想されるように全ての電子が同じエネルギーを持つのではなく,図1に示したような連続分布をしていました。
エネルギー保存は全ての物理学者から強く支持されているので,これは非常に期待を覆した結果でした。最初は誰もこの説明が出来ませんでした。(原子レベルではエネルギー保存が破れているのではないかという提案さえありました。) しかし,1930年12月にウォルフガング・パウリは,チュービンゲンでの会議に有名な論文(英訳はこちら)を書いて提出しました。その論文で彼は,β崩壊において電子と一緒に放出されるスピン1/2の軽い中性粒子の存在を提唱しました。これは上記のエネルギーの連続スペクトルの理由を説明します。それは,エネルギーが電子と検出されない中性粒子の間で分割されるためで,その上いくつかのさらに専門的な非保存問題を解決します。パウリは最初この粒子を“ニュートロン”と呼びましたが,この名前が現在我々が中性子(1932年にジェームズ・チャドウィックによって発見された陽子に似た中性ハドロン)と呼んでいる粒子に与えられると,フェルミはパウリの粒子を“ニュートリノ”(イタリア語で“中性の微粒子”の意味)と呼び変え,それが今日まで引き継がれています。
ニュートリノの発見
フェルミは,1934年に発表されたβ崩壊に関する彼の画期的な理論[1]の中にニュートリノを組み込みました。この理論の成功は,原子核・素粒子物理学者にニュートリノの存在を確心させましたが,その粒子自体は依然として捉えどころのないままでした。実際,パウリは(科学理論は常に検証可能であるべきという原則に反し),決して検出できない粒子を仮定してしまったかもしれないと心配しました。しかし幸運なことに,1930~1940年代に原子核分裂の登場がこれまでになく大強度の(反)ニュートリノ発生源をもたらしました。ここで初めて,この捉えどころのない粒子の実験的検出が現実的な課題となりました。
原子核分裂はニュートリノを生成します。それは,重元素の原子核分裂は,安定となるには多すぎる中性子を含む同位体を作りだすためで,過剰な中性子は陽子に転換した方がエネルギー的に有利なため,次々とβ崩壊が起こることになります。膨大な数のニュートリノは検出される確率を非常に大きくします。それはちょうど宝くじを当てるようなもので,たとえ1つ1つのニュートリノの検出確率(当たりの券を引く確率)が非常に小さくても,ニュートリノが十分多く生成されれば,そのうちのいくつかは検出されやすくなります。(宝くじで,十分たくさんの券を買えば,おそらく少なくとも1枚が当たりになるのと同じです。)
第二次世界大戦中から戦後にかけて,物理学者フレッド・ライネスはロスアラモス研究所で働き,核兵器の試験にも携わっていました。1951年,彼のノーベル賞受賞記念講演でも述べたように,彼は何か基礎的な物理学を研究したいと心に決め,何ヶ月か考え抜いた後,彼が言うには「私が潜在意識から浚い上げることができたのは,核爆弾をニュートリノの直接検出に使えないかということでした。」 実験家のクライド・カワンと共同で,ライネスは必要な検出器のデザインに着手しました。それは1950年代の標準からは余りに大きなもので,約1m3に及びました。(対称的に,現在のスーパーカミオカンデ検出器は50,000m3の体積を持っています。) 検出器が非常に大きいというだけではなく,それは核爆発の中心に近いところで壊れずにいなければならず,また核爆発の火の玉が消失するより前にデータが得られる時間は数秒しかないという困難を伴っていました。これは相当な技術的挑戦でした。
ライネスとカワンが使うことにした反応は νe + p → e+ + n という逆β崩壊で,新たに開発された技術である有機液体シンチレータを使って検出することができました。この反応は,陽電子が電子と対消滅して2個のγ線(高エネルギーの光子)を生成するときに最初の光を出します。中性子は数マイクロ秒間移動した後,原子核に捕獲され,その原子核が基底状態に落ちるときにもう1つのγ線を作ります。ライネスとカワンは,特徴的な時間差で分けられた2つの信号の“遅延同期”によって,実験のバックグラウンドが大きく軽減されることに気付いていくらか安心しました。そのことは,核爆弾に頼らなくても,それよりも弱い原子炉からのニュートリノのフラックス(流束)使って実験することを可能にしました。
1953年にハンフォードの研究施設で行われた最初の実験では,信号をかすかに示唆する結果を得ましたが,予想よりも遥かに高いレベルのバックグラウンドに悩まされました。ロスアラモス研究所に戻ってテストを繰り返すと,これは宇宙線のためであり,検出器を地下に設置することで表土が宇宙線の多くを吸収し,バックグラウンドを減らせることが分かりました。検出器は,中性子捕獲の効率を上げるために,検出媒体中にカドミウムを含むようデザインし直されました。カドミウムは中性子に対して非常に高い親和力を持ち,そのため原子炉の制御棒にも使われています。彼らはまた,サウスカロライナ州に新たに建設されたサバンナリバーの原子炉に研究を移しました。そこには,原子炉の中心から11m離れた地下12mのところに検出器を設置できるちょうどいい場所がありました。より強力な原子炉と感度のより高い検出器,および宇宙線に対するよりよい遮蔽によって,信号は一時間当たり3.0±0.2事象のはっきりしたものに向上しました。ニュートリノがついに観測されたのです。
異なるタイプのニュートリノ
1956年には,電子とミューオン(タウは1975年まで未発見)という2種類の荷電レプトンが知られており,それらは質量の違いにより簡単に区別することができました。これらにはそれぞれ反対の電荷を持つ反粒子がありました。したがって,ニュートリノの実験的観測によりすぐに出てくる疑問は
- ニュートリノはその反粒子と区別できるのか?
- π+ → μ+ ν などでミューオンとともに生成されるニュートリノは,β崩壊などで電子とともに生成されるニュートリノと異なるのか?
というものでした。最初の疑問にはすぐに答えることができました。塩素の重い同位体である塩素37は逆β崩壊 ν + 37Cl → 37Ar + e– によってアルゴン37に転換することができます。全てのレプトン数から全ての反レプトン数を引いた数が反応の前後で常に一定であるというレプトン数保存則に従って,この反応は反ニュートリノではなくニュートリノを含むはずです。反対にβ崩壊では,電子とバランスするように反レプトンが作られるので反ニュートリノを含むはずです。したがって,もしニュートリノと反ニュートリノが異なる粒子であれば,原子炉からのニュートリノは塩素37をアルゴン37に転換しないと考えられます。
レイ・デービスは,後に太陽ニュートリノに関する業績で有名になりますが,ブルックヘブン研究所の研究用原子炉をニュートリノ発生源に使い,四塩化炭素(CCl4)を標的にしてこの過程を詳しく調べました。1955年~1960年にかけて,デービスはこの反応の確率が,ニュートリノと反ニュートリノが同一粒子であると仮定した場合に予想される確率の10%よりも小さいことを示すことができました。この業績はニュートリノと反ニュートリノが異なる粒子であり,またレプトン数保存則が弱い相互作用で成り立っていることを示しました。
2番目の疑問には,ほとんど常にミューオンを伴って崩壊するパイ中間子(π → μ ν であって,π → e ν ではありません)を用い,そのパイ中間子の崩壊で生成されるニュートリノが,その後電子に転換できるかどうかを調べることで答えることができます。もし電子への転換ができたら,2つの型のニュートリノには違いがないことになります。この実験には加速器が必要で,なぜなら放射性崩壊に伴うエネルギーはパイ中間子やミューオンを直接生成するには程遠く小さいからです。
実験は1962年にブルックヘブン研究所で行われました。[2] ブルックヘブンAGS加速器を用いて,15GeVの陽子ビームを生成しました。これらの陽子は標的(この場合はベリリウム)に当たってパイ中間子を生成し,そのパイ中間子は飛行中にミューオンとニュートリノに崩壊します。さらにその下流に設置した13.5m厚の鉄の遮蔽壁が,ニュートリノ以外の全ての粒子を吸収します。その結果,ミューオンに伴う約1GeVまでのエネルギーを持ったニュートリノビームになります。(さらに高いエネルギーではK中間子で生成されるニュートリノからの寄与があり,ミューオンに伴って生成されたことが保証されなくなります。)
実験では34個のミューオンの飛跡が検出され,そのうち5個は宇宙線のミューオンによるバックグラウンドと見積もられました。もしパイ中間子の崩壊によって生成されるニュートリノが,β崩壊で生成されるニュートリノと同一であるならば,29個の電子事象が起こると期待されました。(実験で電子事象を検出する効率が約2/3なので,実際には彼らは20個を得たでしょう。)もしニュートリノが同一でなければ,彼らはおそらく,K+ → e+ + νe + π0 のようなK中間子崩壊からくる電子を伴うニュートリノによって生成される1個か2個の電子を観測すると期待されました。実際には,ミューオンらしくない事象は中性子からのバックグラウンドと矛盾せず,それらは電子らしくはありませんでした。(彼らは検出器を400MeVの電子ビームに照射していたので,電子事象がどのように見えるのかを知っていました。)
したがって,1962年までに,ニュートリノは反ニュートリノとは異なる粒子であること,電子とともに生成されるニュートリノとミューオンとともに生成されるニュートリノ(現在ではそれぞれ電子ニュートリノ νe およびミューニュートリノ νμ と呼ばれている)は異なる粒子であること,そしてレプトン数保存則は電子とミューオンで別々に成り立っていることが明らかになりました。これらの性質はリー,ヤン,ランダウ,サラムによりほとんど同時に作られたモデルによってよく記述され,そこではニュートリノの質量は厳密にゼロとされていました。
皮肉なことに,ニュートリノ物理における最近約15年間の進展はこれら長年にわたって確かめられてきたことを全て覆すことに専ら捧げられてきました。我々は,ニュートリノに質量があること,電子とともに生成されるニュートリノはその後ミューニュートリノとして反応できることを知っています。また我々は,ニュートリノと反ニュートリノは結局異なる粒子ではないのではないかと強く疑っています。(しかし,まだ確かなことは分かりません。) このことは,上に述べた実験が間違っていたとか,ブルックヘブン研究所で行われた2成分ニュートリノ実験に対してレオン・レーダーマンやメル・シュワルツ,ジャック・シュタインバーガーに送られたノーベル賞が相応しくなかったというわけでは決してありません。ニュートリノの質量は極端に小さく,そのため異なるタイプ(フレーバーとして知られている)の間の振動は,ほとんどの実験条件では非常に小さいのです。同じように,ニュートリノと反ニュートリノの区別は,ニュートリノに質量が無い場合,もしくは質量がほとんど無いに等しい場合には,明確もしくはほぼ明確につけられます。非常に感度の高い実験だけが,何年にも及ぶ細心の注意を払った解析を行った末に,これらの僅かな効果を示すことができたのです。
ニュートリノとノーベル賞
ニュートリノ実験は困難で,しばしば画期的でもあります。これが(時々は長い期間をかけて)認められ,ニュートリノ物理の多くの先駆者がノーベル物理学賞を受賞してきました。
| 1988 | レオン・レーダーマン,メルビン・シュワルツ,ジャック・シュタインバーガー | ニュートリノビーム法,及びミューニュートリノの発見を通じてレプトンの2成分構造を明らかにしたことに対して |
| 1995 | フレデリック・ライネス | ニュートリノの検出に対して |
| 2002 | レイモンド・デービス,小柴昌俊 | 天文学への先駆的貢献,特に宇宙ニュートリノの検出に対して |
加えて,ニュートリノ理論への主要な貢献を行ったウォルフガング・パウリ(1945),エンリコ・フェルミ(1938),及びリー,ヤン(1957)が,ニュートリノとは直接はつながりのない業績に対してではありますが,それぞれノーベル賞を受賞しています。ノーベル賞は没後に受賞することはできないので,クライド・カワンはニュートリノの検出に対する遅ればせながらの受賞を分かち合うことは出来ませんでした。