ニュートリノ発生源とニュートリノ実験の原理は,1950年代後半の先駆的な時期以来あまり変わっていません。1960年に書かれたレビュー論文[3]で,フレッド・ライネスは以下にように述べています。
- 原子炉が低エネルギー反ニュートリノの最も適した発生源である。
- ミュー型のニュートリノと反ニュートリノは,それぞれに対応する適切な電荷をもつパイ中間子を飛行中に崩壊させ,その後ニュートリノ以外の生成粒子を分厚い吸収体で止めることで生成できる。
- そのようなニュートリノビームは,ミューニュートリノが電子ニュートリノと異なるかどうかを確認するのに使うことができる。
- ニュートリノ‐電子弾性散乱は,バックグラウンドが制御できる場合には低エネルギーニュートリノを検出するきれいな方法である。
- ν + 37Cl → 37Ar + e– の反応は,太陽ニュートリノを検出するのに使うことができる。
- 水中でのニュートリノ反応によって生成された荷電レプトンからのチェレンコフ放射の検出は有望な手段で,ニュートリノの入射方向の情報を与えることができる。
- 太陽は“ニュートリノの最も大量な発生源”であるが,主要な過程で生成されるニュートリノは非常に低エネルギーであるので,太陽ニュートリノの検出可能性は,ホウ素8やベリリウム7からのエネルギーの高いニュートリノが核融合の側鎖反応でどれだけ作られるかに依っている。
- 地球の大気に衝突する宇宙線は,パイ中間子の崩壊から大量のニュートリノの流束を作る。
- 天体で生成される高エネルギーニュートリノは,銀河磁場で曲げられてしまう宇宙線や厚い物質に吸収されてしまう光子からは得られない情報を与える。
- そのようなニュートリノは,地下深くに設置された体積の大きな検出器を用いて研究することができる。
続く50年にわたるニュートリノ物理を眺めると,これは非常に高い確率で言い当てられています。ただ,単一または二重ベータ崩壊によるニュートリノ質量の研究はここには入っていません。実際,ライネスは数キロトン規模の検出器の必要性など,このプログラムのいくつかの側面は現実的でないと考えていたことは事実です。それにも関らず,ニュートリノによってもたらされる疑問や課題は,この分野の研究の非常に初期の頃からすでに認識されていたことを示しています。しかしながら,それらの課題に取り組んだ結果はそれほど予測できるものではありませんでした。
このページでは,人工的に生成されるニュートリノおよび自然界で生成されるニュートリノに関してその両者の発生源について述べます。次のページでは,これらのニュートリノが実験で検出されるためのいろいろな方法を考えます。
人工ニュートリノ発生源
これまでのところ,人工ニュートリノ発生源は先駆者たちが用いたものとあまり変わっていません。2つの主な種類は,原子炉を使って原子核分裂片のβ崩壊から反電子ニュートリノを生成する方法と,陽子加速器を使って飛行中のパイ中間子崩壊からミューニュートリノ(もしくは反ミューニュートリノ)を生成する方法です。
原子炉ニュートリノ
原子炉は重い原子核(主にウラン235)を小さな断片に壊すことによってエネルギーを生み出します。原子核中の陽子に対する中性子の割合は原子番号が大きくなるにつれて増えるので,これらの核分裂片は中性子を過剰に含み不安定で,陽子に対する中性子の割合が低い安定核へとβ崩壊を繰り返して崩壊します。平均的に個々の分裂は約200MeVのエネルギーと約6個の反電子ニュートリノを放出します。従って,原子炉の出力から1秒あたりに作られるニュートリノの数を見積もることができます。
しかし,ニュートリノ実験はニュートリノの総数だけではなく,そのエネルギー分布も知る必要があります。すなわち,ニュートリノが検出器で反応する確率はエネルギーに依存し,従ってニュートリノ振動のようなそこで研究される物理もエネルギーに依存するということです。これを計算するのはもっと困難な問題で,それは最初のウラン原子核が破砕していろいろな種類の不安定核を生成し,それによってプルトニウム239(1個の中性子がウラン238に捕獲されたときに生成)やプルトニウム241(ウラン238がプルトニウムへβ崩壊する前に数個の中性子を捕獲したときに生成),およびウラン238それ自身(通常は分裂できないが,高速中性子が衝突すると分裂が誘発される)などの付加的な分裂可能核を考慮に入れる必要があるからです。その結果得られるエネルギースペクトルを決定するために2つの方法が取り入れられました。
- 核分裂生成物やそのβ崩壊スペクトルに関して過去60年にわたって集められたデータを用いて,第一原理計算からスペクトルを得ることができます。これは膨大な計算で,まさに何千種類ものβ崩壊の情報を必要としますが,現代のコンピュータ技術を用いて行うことができます。
- β崩壊はニュートリノと同時に電子を生成し,その電子のエネルギーは直接測定することができます。そしてニュートリノのスペクトルは電子のスペクトルから推測することができます。β崩壊に関するいくらかの情報がやはり必要ですが,第一原理計算ほど多くはありません。原子炉から来る電子のスペクトルの詳細な測定が1980年代にグルノーブルのラウエ・ランジュバン研究所にある原子炉を用いて行われました。
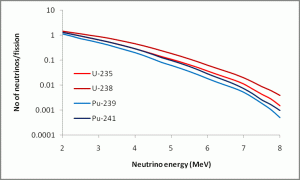
図2:原子力発電に含まれる4つの主な同位体に関して計算した反ニュートリノのスペクトル。スペクトルは1回の核分裂で規格化されている。実際はU-235とPu-239が主要な同位体で,U-238とPu-241が全体の約10%で寄与している。データはT.A. Mueller et al., arXiv hep-ex/1101.2663v3. から引用。
最近の計算結果を図2に示します。ウラン235とプルトニウム239からくる総出力の割合は原子炉の燃料サイクルによって変わりますが,それはプルトニウム239は燃料棒の最初の状態には存在せず,原子炉の中で作られるからです。スペクトルは全て非常に似ており,数MeVのエネルギーを持つ反ニュートリノを生成します。このエネルギーはミューオンの静止質量(mμc2 = 105.7 MeV)よりもずっと小さいので,原子炉で出来る実験の種類は限られます。
これらの計算に費やされた全ての努力にも関らず,我々のスペクトルに対する理解は,依然として原子炉ニュートリノを用いる実験の誤差の大きな原因として残っています。このために現在の原子炉ニュートリノ実験では,原子炉の近くに置かれる前置検出器と,慎重に選んだ距離(ニュートリノ振動の章を参照)を離して置かれる後置検出器の2つの検出器を使います。そして前置検出器と後置検出器の比は,ビームの性質が距離とともにどう変化するかを調べるために用いられ,原子炉ニュートリノの流束の不確かさは大きく相殺されます。
加速器ニュートリノ
陽子加速器からのニュートリノビームは以下のように生成されます。
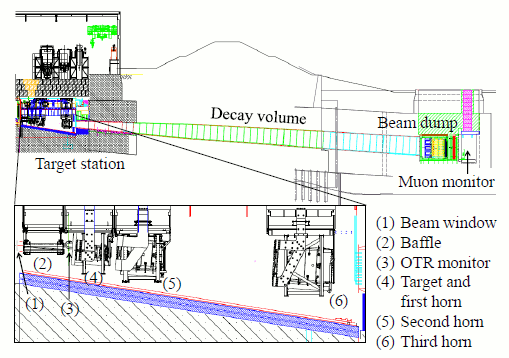
図3:標的ステーションからビームダンプまでのT2Kニュートリノビームライン。ビームラインの構成要素が図中にラベルされている。“OTR”は“optical transition radiation”の略で,陽子ビームが標的に当たる前にそのプロファイルをモニターするのに使われる。標的を囲んでいる第1ホーンは正電荷のパイ中間子を集めるのに使われ,第2ホーンと第3ホーンはそれらを細い平行ビームへ収束するのに使われる。バッフルは陽子ビームが偶然軌道からずれたときに第1ホーンを守る。
- 陽子は標準的な粒子加速器(通常はシンクロトロン)で加速されます。陽子のエネルギーは,ビームラインの配置とともにニュートリノのエネルギーを決定します。
- 陽子ビームは加速器から引き出され,標的へと向けられます。陽子は標的物質と反応し,大量の2次パイ中間子が他の粒子とともに作られます。
- 成型された磁場(収束ホーン)が電荷(ニュートリノビームには正電荷,反ニュートリノビームには負電荷)を選択するのに用いられ,細い平行なビームへと収束されます。
- ビームは長い崩壊領域へと向けられ,そこではパイ中間子がミューオンとニュートリノ(または反ニュートリノ)へと崩壊します。荷電パイ中間子は0.026μs(10億分の1秒の26倍)の平均寿命を持ちますが,ミューオンはほぼ100倍の寿命(2.2μs)です。崩壊領域の長さは,パイ中間子のほとんどが崩壊しミューオンはほとんど崩壊しないようになっています。(これを計算するときには相対論的な時間の伸びを考慮する必要があります。パイ中間子は光速に近い速さで飛んでおり,その内部時計は静止している観測者よりもゆっくりと進むので,パイ中間子は0.026μsよりもずっと長く飛んでいるように見えます。したがってT2K実験の崩壊領域の長さは96mもあり,単純な計算から期待される6.6mではありません。
- 崩壊領域の最後にはビームダンプがあります。これはニュートリノ以外の全ての粒子を吸収する大きな質量を持つ物質です。(ただし,いくらかのミューオンはこれを通り抜け,ビームの位置と強度をモニターするために使われます。)
この結果,ほぼ純粋なミューニュートリノ(もしくは負電荷のパイ中間子の場合は反ミューニュートリノ)のビームが作られます。ニュートリノのエネルギースペクトルはビームパラメータから計算することができ,これは原子炉ニュートリノのスペクトルを計算するよりもかなり簡単な作業です。さらにまたニュートリノのエネルギースペクトルはミューオンのスペクトルから引き出すこともできます。いくらかの避けられない電子ニュートリノの混入がありますが,これは最初のパイ中間子ビームにはいくらかのK中間子もまた含まれるためで,K中間子は崩壊して電子ニュートリノを作ることができます。したがって加速器を用いたニュートリノ実験では,原子炉ニュートリノ実験のように,一般的に後置検出器だけではなく前置検出器も用います。
このように生成されたニュートリノビームのエネルギースペクトルはかなり広い分布をしています。図4はフェルミ加速研究所のMINOS検出器で使われたビームを示しています。これはビームの向きを後置検出器の方向からわずかにずらすことで大きく改善されます。このようなオフアクシスビームは,強度が減る代わりにエネルギーの広がりをずっと狭くできます。もし陽子ビームの強度が十分強ければ,この方法は価値のあるトレードオフになります。T2K実験では比較的よく決まったエネルギーのニュートリノビームを作るためにオフアクシスビームを用いています。
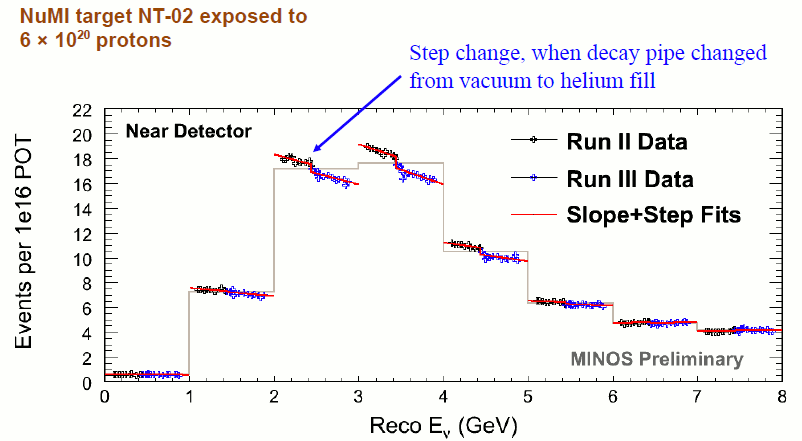
図4:MINOS実験のビームにおける再構成されたニュートリノエネルギースペクトル。時間とともに強度が僅かに減少を示しているが,これは標的の経時変化から来ていると考えられる。図はMINOS実験の公式ウェブページから引用。
将来的技術
加速器の性能は劇的に向上してきましたが,加速器からニュートリノビームを作る上記の方法は,フレッド・ライネスが1960年に書いたレビューで述べ,レーダーマン,シュワルツ,シュタインバーガーがノーベル賞を受賞した1962年の実験で建設したものと概念的には変わっていません。現在生成可能な全てのニュートリノビームはこのように作られていますが,全く新しい技術的方法が次世代に向けて開発されようとしています。
β崩壊では非常に純度の高い反電子ニュートリノ(電子が放出された場合)または電子ニュートリノ(陽電子が放出された場合)が生成されますが,ニュートリノのエネルギーは多くの実験技術にとっては低すぎます。特にE < mμc2より,ニュートリノはミューオンに転換できません。(そしてさらに重いタウはなおさら無理です。)ベータビームのアイデアは,放射性同位体から電子を剥ぎ取って正に帯電したイオンを崩壊する前に高エネルギーに加速することによって,ニュートリノのエネルギーを上げようとするものです。この方法では作られるニュートリノのエネルギーは増加し,非常に細いビームになります。もし選ばれた同位体が電子捕獲(陽電子とニュートリノを放出する代わりに,自らの軌道電子を捕獲しe– + p → νe + n によってニュートリノのみを放出)によって崩壊するならば,ビームは非常によく決まったエネルギーを持つことになります。しかしこれは非常に困難で,なぜなら原子核が加速される間,その原子核が1個の電子を軌道に保っていることを保証しなければなりません。(もし捕獲される電子が無ければ電子捕獲による崩壊はできません。)
ベータビームは短寿命の人工の同位体を使う必要があります。炭素14のような長寿命の同位体では十分なニュートリノを作れないからです。LHCが鉛を衝突させるのに使われているようにイオンの加速はよく確立された技術ですが,非常に短寿命のイオンには特別な問題があります。イオンの多くが崩壊してしまう前に短時間で収集と加速を済ませてしまわなければいけません。そしてそれらが崩壊すると電荷がなくなるのでビームから失われ,加速器の物質を放射化させてしまいます。加速器に対してもそこで作業をする人に対しても放射線安全対策やそのための装置が重要な問題になります。
これまで誰もベータビームを作っていませんが,その技術はイオンの加速と蓄積において専門知識が豊富なCERNにおいて特に精力的に研究されています。
究極の加速器ニュートリノがニュートリノファクトリー(工場)です。そこでは,粒子加速器に蓄えられたミューオンの崩壊によってニュートリノを生成します。ミューオンはμ+ → e+ νe νμによって崩壊しますが,これは非常に単純かつよく理解されており,ニュートリノのスペクトルは非常によい精度で計算することができます。ビームは混合ビームですが,反ニュートリノは全てミュー型でニュートリノは全て電子型です。(もしμ–が使われた場合は反対になります。)したがって,もし検出器がニュートリノ反応によって生成される電子やミューオンの電荷を決定できるならば,それらは簡単に判別できます。(反ニュートリノは常に正の電荷を持つレプトンに転換し,逆もまた同じです。)
これは強力で素晴らしい方法です。問題はミューオンの平均寿命がたった2.2マイクロ秒だということです。相対論的な時間の伸びによってその寿命は大きく引き伸ばされますが,50GeVに加速されたミューオンでも崩壊するまで1ミリ秒ほどしかありません。このことはミューオンは細く絞られたビームを作るためにランダムな運動を抑えられ,すなわち“冷却”され,さらに続く加速と蓄積を非常に短時間で行わなければならず,これは非常にチャレンジングな技術的課題です。理論的な研究では,ニュートリノファクトリーは我々のニュートリノに対する理解を深めるのに最も大きな可能性を持っていることが示されており,この技術的挑戦への取り組みが行われています。例えば,ミューオンイオン化冷却実験(Muon Ionization Cooling Experiment: MICE)では,パイ中間子の崩壊から生成されたミューオンが加速と蓄積に適当なビームに実際に冷却できることを示すことを目的に研究が進められています。しかしまだ極めて初期の段階で,ニュートリノファクトリーが稼働するには少なくともあと10年は必要になるでしょう。
天体物理学的なニュートリノ発生源
ニュートリノ物理における最も重要な発見の一つであるニュートリノ振動現象は,人工ニュートリノ発生源を使って得られたのではなく,太陽および地球大気で自然に生成されるニュートリノを用いて得られました。宇宙からのニュートリノは,ニュートリノ物理だけではなく超新星や活動銀河といった重要な天体物理学現象に関する情報をもたらしてくれます。
太陽ニュートリノ
1920年にアーサー・エディントン卿が初めて示唆したように,太陽は水素をヘリウムへと核融合することでエネルギーを生み出しています。ヘリウムは2個の水素と2個の中性子を含むのに対して水素には陽子だけしかないので,この過程は必然的に陽子を中性子に転換しなければならず,したがってニュートリノを放出します。これが行われる過程は陽子・陽子連鎖反応と呼ばれ,1930年代の後期にハンス・ベーテによって研究されました。図5[4].にこの過程を示します。
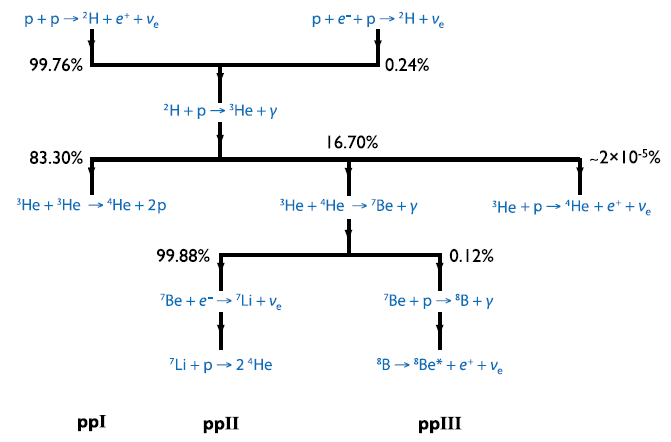
図5:陽子・陽子連鎖反応。主要な分岐と分岐比を示した。一連の反応で放出されるニュートリノはpp(左上),Be-7(ppIIの分岐),B-8(ppIII),pep(右上)およびhep(右中央)として知られている。図は参考文献4から引用。
太陽からのニュートリノの流束は膨大で,1平方センチメートルの面積に1秒あたり約600億個のニュートリノが届いています。ニュートリノの反応のしにくさを考えても,太陽ニュートリノを検出することはかなり現実的な課題です。残念ながら,太陽ニュートリノの大部分は最初の重水素生成p + p → 2H + e+ + ν (ppニュートリノ)から来ており,これらは0.42MeV以下という非常に低いエネルギーしか持っていません。ニュートリノを検出するほとんどの方法ではこのような低エネルギーニュートリノには感度がなく,したがってほとんどの実験では,pp-IIおよびpp-III側鎖で作られるエネルギーのより高い7Beニュートリノや8Bニュートリノに頼っています。(pepニュートリノやhepニュートリノ(図5を参照)も高いエネルギーを持ちますが,非常に頻度が少なくなります。)
太陽ニュートリノはレイ・デービスにより塩素への捕獲反応ν + 37Cl → 37Ar + e–を用いて初めて検出されました。この反応は0.814MeVより高いエネルギーを持つ電子ニュートリノに対してのみ感度があるので,主に7Beや8Bからのニュートリノを検出します。(図6を参照) よく知られているように,実験では期待されるニュートリノの数の約1/3しか検出されず,太陽ニュートリノ問題の発端となりました。最初はこれが“太陽の問題”(太陽構造の理論的モデルがあまり正しくない)なのか“ニュートリノの問題”(ニュートリノの理論的モデルが正しくない)なのか,もしくは実験の問題(デービスによる37Arの検出効率の計算が正しくない)なのか,明確ではありませんでした。2番目の解釈が正しいことが検証されるまでに多くの年月と多くの実験や観測が費やされました。
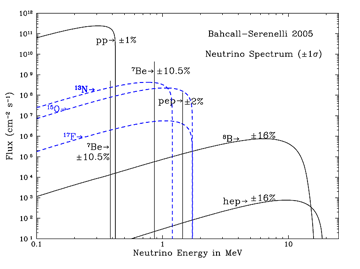
図6:太陽ニュートリノのエネルギースペクトル。ほとんどの太陽ニュートリノ検出器では,エネルギーの関係で主にBe-7ニュートリノとB-8ニュートリノが検出される。青い点線はCNOサイクルからのニュートリノスペクトルで,太陽のエネルギー生成の約1%に寄与している。図はジョン・バコールの論文から引用。
太陽ニュートリノはニュートリノ振動を研究する手段となってきました。太陽ニュートリノ観測の結果は,今日でもニュートリノ混合角を計算するための鍵となる入力情報となっています。
超新星ニュートリノ
超新星は恒星の爆発的な最期を知らせます。短い期間に,爆発する恒星はそれを含む銀河全体に匹敵する明るさになります。1006年に見られた超新星は,7000光年離れているにもかかわらず金星よりもずっと明るく,何週間もの間昼間でも見えたと伝えられています。天文学者にとって残念なことに,1604年に観測されたケプラーの超新星以来,我々の銀河系内で超新星は観測されていませんが,大マゼラン雲(銀河系の衛星銀河で,約160000光年離れたところにある)の中に観測された超新星1987Aは,ニュートリノ発生源として間違いなく検出された太陽以外のただ一つの天体としてその名を知られています。
超新星には主に2つのタイプがあります。Ia型超新星は全てが非常に似た固有の明るさを持つために宇宙論研究者に広く使われていますが,これは重くなりすぎた白色矮星が,重力に対して自身を支えることができなくなって爆発してできたと信じられています。Ia型超新星は最も明るいタイプの超新星(SN1006はおそらくIa型)ですが,あまり多くのニュートリノを作らないと考えられています。
コア崩壊型超新星(スペクトルや光度曲線の詳細によってIb, Ic, IIb, II-P, II-Nなど様々に分類される)は巨大質量の恒星が最期を迎えたときにできます。全ての恒星は核融合反応からエネルギーを生成しており,最初は水素がその燃料として使われます。恒星の中心領域で水素を使いきると,太陽のような恒星は最終的にヘリウムを炭素に融合する反応(水素の融合のときの1000万度に対して約1億度という非常に高い中心温度が必要)に切り替わり,その後白色矮星となって一生を終えます。太陽の8倍よりも重い恒星は,さらに重い元素の融合過程を続けることができ,最後には鉄のコアを作ります。
鉄は最も安定な元素で,重い側および軽い側の両方の元素よりも原子核の束縛エネルギーが大きくなっています。鉄よりも軽い元素は核融合によってエネルギーを解放でき,反対に鉄よりも重い元素は核分裂によってエネルギーを解放できますが,鉄に対してはエネルギーを解放することができません。結果として,いったん恒星が鉄のコアを作ってしまうと終わりです。コアが重くなりすぎて重力に対して自身を支えられなくなると,それは崩壊し,これらの極めて高温高圧な条件下で陽子と電子は結合して中性になってニュートリノを放出します。非常に高温なのでさらに多くにニュートリノがニュートリノ・反ニュートリノ対として熱的に生成されます。我々にとって劇的に見えるのは超新星からの輝く光ですが,実はコア崩壊型超新星によって解放されるエネルギーの99%はニュートリノとしてやってくるのです。
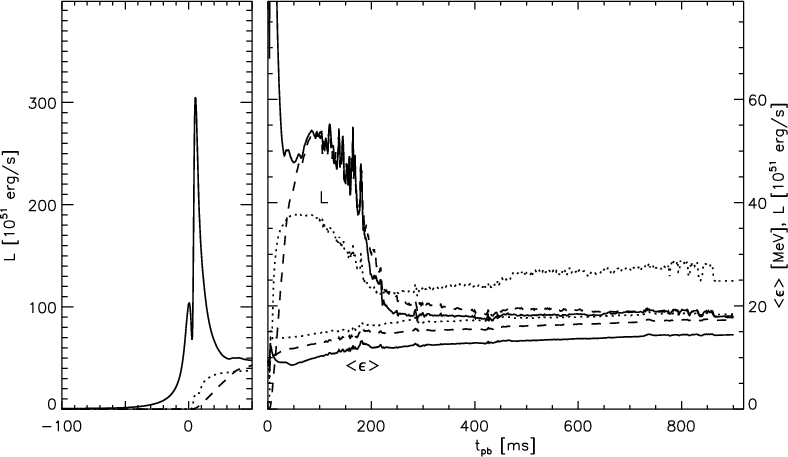
図7:太陽の15倍の質量を持つ恒星によって作られたコア崩壊型超新星からのニュートリノスペクトルのシミュレーション。実線はνe,破線は反νe,点線はその他すべての種類。左図で上の線は輝度で,下の線は平均エネルギー。t = 0での鋭いピークは,コアの陽子が中性子に転換したときの中性子化パルスで,残りのニュートリノは熱的に作られる。このスペクトルは崩壊するコアから400km離れた観測者に対する計算である。図は参考文献5から引用。
ニュートリノはコア崩壊型超新星の理解に極めて重要です。シミュレーションはニュートリノの寄与なしには恒星は爆発しないことを示しています。崩壊する恒星の外殻が新たに作られた中性子星に衝突するときに衝撃波ができるのですが,高密度の媒質の中で止まってしまい,それはニュートリノによってのみ再開されます。コア崩壊型超新星における“ニュートリノ駆動風”は重元素を生成するいわゆるr過程にとっても好ましい状況です。r過程は鉄よりも重い元素の存在量の約半分に重要な役割を果たしています。したがって,コア崩壊型超新星におけるニュートリノ生成は銀河の化学的進化を理解する上で不可欠な要素となっています。その上,ニュートリノは恒星の崩壊において光よりもずっと深いところからやってくるので,初期の中性子星にずっと近い状態からの情報をもたらしてくれる潜在的可能性を持っています。
超新星1987Aからのニュートリノ
SN1987Aは1987年2月24日のちょうど世界時(UT)で深夜になった直後にイアン・シェルトンによって発見されました。それはほぼ過去400年間で初めて肉眼で見える超新星でした。続いてそれ以前に撮影された写真を解析すると,その超新星は約14時間前に見えていました。(超新星になる前の星が12等星だったのに対して,その頃は6等星の明るさになっていました。)それ以前にはSanduleak –69° 202と呼ばれて登録されていた太陽の約20倍重い青色超巨星の爆発だったことが分かり,初めて超新星の親星に対してスペクトルを含む質の良い情報が得られました。現在見つかっている他の全ての超新星は,個々の恒星の情報が通常得られないずっと遠くの銀河で観測されてきました。
SN1987Aに伴ったニュートリノバーストが,星が可視光で明るくなったと最初に観測される約3時間前(そしてその星が確かに明るくなっていないと最後に観測された約5時間後)の2月23日7:35:41 UTに観測されていました。8個のニュートリノがアーバイン・ミシガン・ブルックヘブン(IMB)実験で,11個のニュートリノがカミオカンデII実験(両者とも水チェレンコフ検出器)で観測されました。さらにバクサンの液体シンチレーター検出器でも5事象がこれらと同時刻に観測されましたが,この信号は統計的にあまり有意ではありませんでした。モンブランの液体シンチレーター検出器で約4.5時間前に観測された明らかに有意なバーストは,他のどの検出器中の信号にも対応していませんでした。同じコア崩壊から5時間離れて2回のニュートリノバーストが起こることは理解しがたく,さらに大きなカミオカンデII検出器ではそのとき何も見えていませんでした。(IMBはエネルギーの閾値がずっと高いので,これらの事象はあってもおそらく見えなかったでしょう。)
SN1987Aからのニュートリノは非常に多くの理論的関心を引き起こしました。知られていたニュートリノの反応率と検出されたニュートリノのエネルギーから,SN1987Aがニュートリノで解放したエネルギーの総量を(2倍以内の精度で)算出することができ,答えは約3×1046 Jでした。これは(E = mc2を使って)3×1029 kgの質量に対応します。これは太陽の質量の約1/6で,コア崩壊型の超新星によって解放されるエネルギーのほとんどがニュートリノの形であることを証明します。中性子星の束縛エネルギーの計算とも矛盾していません。
原理的に超新星からのニュートリノの時刻とエネルギー分布は超新星爆発に関して,およびおそらくはニュートリノ物理に関しても非常に多くのことを教えてくれることでしょう。SN1987Aからの検出された数が単純に少なすぎてあまり多くのことが出来なかった-にもかかわらずSN1987Aに関して膨大な数の理論の論文が発表されている-のですが,我々の銀河の中で起こる超新星はおそらく5倍は地球に近く,今日の大きな検出器(スーパーカミオカンデはカミオカンデIIの25倍の大きさ)では何千ものニュートリノが検出されるでしょう。あとは希望を持って待つだけです!
大気ニュートリノ
地球は常時一定の割合で宇宙からの飛来する宇宙線を浴びています。地球大気の外側には主に陽子があり,その約10-15%の割合でより重い原子核も存在しています。これは星間物質の一般的な化学組成と同じになっています。それらが大気に当たると,高エネルギーの陽子は空気の分子と反応してパイ中間子のシャワーを作ります。これは引き続いて崩壊しミューオンとミューニュートリノになります。ミューオンのいくらかは地表に到達して宇宙線として検出されますが,その他は飛行中に崩壊し,さらにミューニュートリノと電子ニュートリノを生成します。この過程は粒子加速器からニュートリノビームを生成するために用いられたものと正に似ています。もし全てのミューオンが地表に到達する前に崩壊していたら,1個の電子ニュートリノに対して2個のミューニュートリノ(ミューオン生成に付随した1個のミューニュートリノと,そのミューオンが崩壊したときに生成されるもう1個のミューニュートリノ)を観測することが期待されます。しかしそれらの全部は崩壊しないので,実際に期待される比はいくらかこれよりも大きくなります。大気ニュートリノの初期の観測では,いくつかの実験ではおよそ期待通りの比が観測されたのに対し,その他の実験では期待よりもかなり少ないミューニュートリノしか観測されない(大気ニュートリノ異常)という相反する結果が出てきました。何年かの間この不一致が続いた後,スーパーカミオカンデからのデータが,この欠損は本物でさらにニュートリノ振動の結果であるということを最終的に皆に納得させるに至りました。同じくニュートリノ振動の可能性を研究していた太陽ニュートリノ実験にとってはいくらか辛いところでしたが,この大気ニュートリノ観測の結果が,一般的にはニュートリノ振動の最初の決定的な証拠と見なされています。
大気ニュートリノのもととなる一次宇宙線が広大なエネルギー範囲で存在しているので,大気ニュートリノも非常に広いエネルギーの範囲で生成されます。視点次第で,それらはニュートリノ振動を研究する非常に有益な実験室にもなり,また天体物理的発生源からの高エネルギーニュートリノを探索するためには鬱陶しいバックグラウンドにもなります。確かに,フレッド・ライネスの1960年における考えでは大気ニュートリノはあまり本質的な興味にはならないだろうということでしたが,結局それはあまりに悲観的すぎた考えだったと分かりました。
天体物理学的な加速機構からのニュートリノ
大気ニュートリノは宇宙線が我々の大気と反応して生成されます。しかし,宇宙線自体はどこから来るのでしょうか? この疑問には簡単に答えることができません。なぜなら,宇宙線は荷電粒子なのでそれらが宇宙空間を飛んでいる間に銀河磁場によって曲げられてしまうからです。それらが地球の大気にぶつかるまでに,その方向はもはや生成された位置の情報を与えてはくれません。もっともらしい理論は,ほとんどの宇宙線は超新星残骸-星の爆発の後に残された膨張するガス-から来ているが,一方で最高エネルギーなどは活動銀河またはガンマ線バーストが起源であると示唆しました。しかしこれらの仮定を証明するものは何もありません。
それらが何であれ,宇宙線の源は明らかに陽子を非常に高いエネルギーに加速しています。これらの高エネルギー陽子のいくらかが他の粒子または陽子と発生源の中で衝突してパイ中間子を生成し,よってニュートリノを生成することは必然的です。したがって,全ての高エネルギー陽子の発生源は,それよりは幾分低いエネルギー(ニュートリノはそれらを生成する陽子のエネルギーのほんの一部分を持ち去るだけです。)を持つ高エネルギーニュートリノの発生源にもなっているはずです。これらのニュートリノは銀河磁場の影響を受けないので,それらを観測すれば天体物理的な粒子加速機構を持つ場所に対する明らかな証拠となることでしょう。
これは困難な作業です。ニュートリノの数は原子炉や加速器,太陽や超新星からの流束に比べて小さく,したがって検出器はこれを補うために極めて大きくする必要があります。加えて,宇宙ミューニュートリノから作られるミューオンの同定は,大量の宇宙線ミューオンのバックグラウンドや,それよりも少ないけれどもより区別が困難な大気ミューニュートリノからのバックグラウンドがあるために複雑です。1つ目のバックラウンドは,空から下向きにやって来るミューオンの代わりに地球を通って下から上向きに来るミューオンを探すことで軽減することができます。ニュートリノは簡単に地球を通り抜けることができますが,宇宙線ミューオンは止まってしまうからです。2番目のバックグラウンドは避けられません。(大気ニュートリノは本物のニュートリノだからです。)ただ測定して信号から差し引くだけです。
非常に大きな検出器の必要性は,タンクの水の代わりに自然の水をチェレンコフ光の放射体として使うことで満たされます。3つの現在稼働しているニュートリノ望遠鏡,IceCube, ANTARES, Baikal はそれぞれ南極の氷,地中海,バイカル湖を使っています。宇宙線のバックグラウンドを減らすために,それらは全て少なくとも水面(もしくは氷上)から1km以上深いところに設置され,IceCubeは北の空を見るために,ANTARESとBaikalは南の空を見るために全て下を向いています。これらのどの実験からも宇宙起源のニュートリノのもっともらしい信号を観測したという報告はまだありませんが,今のところはまだ少ない統計に制限されてしまっている状況です。
暗黒物質からのニュートリノ
暗黒物質の性質は,現代宇宙論の中で最も興味深い未解決問題の1つです。銀河の回転曲線から宇宙背景放射の構造にわたる幅広い観測は,宇宙に存在する物質の約85%は通常のバリオン物質ではなく,何かエキゾチックなタイプの弱い相互作用をする粒子であることを示しています。一時期,ニュートリノがそれ自身この不思議な物質の候補と考えられたこともありましたが,我々が今見ている宇宙の構造と矛盾が無いためには,ニュートリノの速度はあまりに光速に近すぎると今では見なされています。(銀河が形成されるときに,銀河の重力によってその軌道に束縛されるにはニュートリノはあまりに速すぎるが,観測は暗黒物質が銀河に束縛されていることを示しています。) それでもなお,ニュートリノが暗黒物質問題を解決する手助けになる可能性はまだあります。
暗黒物質の候補の1つが,(まだ確立されていない)超対称性理論によって予言されるニュートラリーノχです。もし存在すれば,ニュートラリーノは暗黒物質に適した性質を持っています。中性で,ほとんどの超対称性理論において安定で,(おそらく陽子の100倍は)重く,しかも弱い相互作用をします。それらは他の粒子と一緒に宇宙の非常に初期,すなわち温度が非常に高く,全てのものがLHCのビームエネルギーと同じくらいのエネルギーを持っていた頃に生成され,今日まで安定に生き残ってきたと考えられます。
ニュートラリーノはそれ自身が反粒子であるという興味深い性質を持っており,したがって2つのニュートラリーノは対消滅して新たな粒子反粒子対を作ることができます。それらは直接ニュートリノ反ニュートリノ対を作ることはできませんが,それらが生成する粒子対(例えばZボソンやWボソン,ヒッグス粒子,もしくは重いクォーク反クォーク対)は続いてニュートリノに崩壊することができます。したがって,ニュートリノ生成はニュートラリーノ生成を示す信号になるかもしれません。
問題はもちろんニュートラリーノが弱い相互作用をすることで,そんなに簡単には対消滅しません。もしニュートラリーノの質量が150GeVの場合,地球近傍では1立方メートルあたりおよそ3000個のニュートラリーノがある計算になります。これは沢山に聞こえますが,検出できるほどの対消滅率になるには全く十分ではありません。(地球には1平方センチメールあたり600億個の太陽ニュートリノが来ていますが,それらは検出するのが十分難しいことを思い出して下さい。) 幸いなことに,ニュートラリーノは太陽のような大きな物体に重力によって捕獲されることが可能で,時間がたつと太陽のコアに沈んでいきます。超対称性粒子はまだ1つも発見されていないので,理論計算は正確ではなく,したがって方程式にどういった数を入力すればいいのか我々は知りませんが,少なくとも太陽のコアでのニュートラリーノ対消滅はニュートリノ望遠鏡で観測できるだけのニュートリノの流束を作ることが可能であると示唆しています。これらのニュートリノは,ニュートラリーノの質量にも依りますが,典型的に数十から数百GeVのエネルギーを持つとされています。宇宙の加速機構からのニュートリノほど高くはないですが,核融合や超新星爆発からのニュートリノよりは随分高いエネルギーです。このニュートリノの信号が実は太陽のコアでのニュートラリーノ対消滅を検出する唯一の方法で,その他の全ての対消滅からの生成物は太陽内部の高密度の物質によって吸収されてしまいます。



